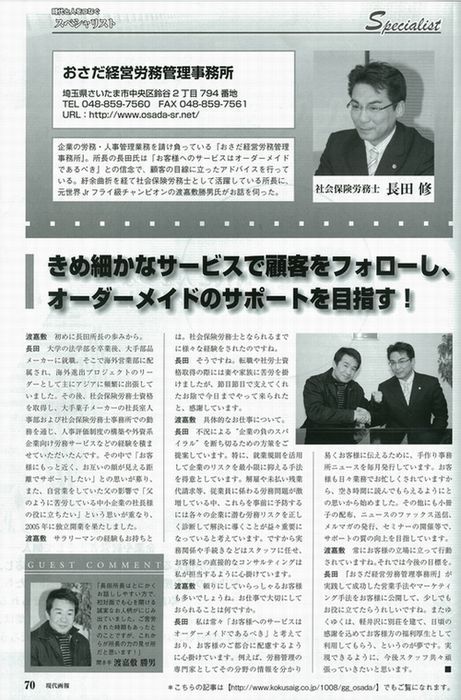(5)居住用財産の買換え等に係る特例措置(譲渡益に係る課税繰延べ、譲渡損に係る損益通算及び繰越控除)について、譲渡益に係る課税繰延べの場合の譲渡資産価格要件を見直したうえで2年間延長
(6)マンション建替事業に係る特例措置(権利変換により資産を取得した場合の課税特例等(所得税、法人税)、権利変換手続開始の登記等に対する免税(登録免許税))の適用対象を拡充(登録免許税は併せて2年間延長)
2.災害に強い都市・地域の形成
(1)東日本大震災により被災したため従前と異なる場所に鉄道線路が移設される場合における用地取得に係る不動産取得税の非課税措置の創設
(2)特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された特定都市河川流域内において設置される一定の雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の軽減措置について、特例率(参酌する割合は2/3)を条例に委任する仕組みを導入したうえで3年間延長
3.地域公共交通の維持・活性化等
(1)公共交通機関のバリアフリー促進のため、新たに取得するホームドアシステム及び鉄道駅のエレベーターに係る固定資産税等の軽減措置(5年間2/3)を創設
(2)JR北海道、四国及び九州に係る三島特例(固定資産税等1/2)、JR三島会社・JR貨物に係る国鉄承継特例(固定資産税等3/5)の5年間延長等
(3)地方航空路線維持のため、国内線航空機に係る固定資産税の軽減措置(B737、B787等の中小型機:5年間2/5、B777等の大型機:3年間2/3)の2年間延長
(4)運行維持が困難な条例で定める路線の乗合バス車両に係る自動車取得税の非課税措置及び鉄道事業再構築事業に係る固定資産税の軽減措置(5年間1/4)の2年間延長
4.船舶、鉄道、建設機械その他の機械装置等の動力用軽油に係る軽油引取税の非課税措置の延長
小型旅客船、海上保安庁等の船舶、非電化区間等の鉄道及び建設機械その他の機械装置等の動力用の軽油の非課税措置について3年間延長
◎成長戦略・地域の経済活性化関連税制
1.成長戦略関連税制
(1)トン数標準税制について、更なる経済安全保障を確保する観点から、次期通常国会における海上運送法の改正、「日本船舶・船員確保計画」の拡充を前提に、平成25年度税制改正において、その適用範囲を一定の外国船舶(準日本船舶(仮称))にも拡大(平成25年4月以後開始事業年度から適用)
(2)国際船舶に係る登録免許税の軽減措置の2年間延長(本則4/1000→3.5/1000)及び固定資産税の軽減措置の3年間延長・拡充(現行1/15→1/18)
(3)船員に係る個人住民税に関し、自治体独自の減免等を制約する平成元年の内かんは拘束力を持たないこと、減免は各自治体判断で可能なこと等を総務省より自治体に周知
(4)国際戦略港湾における指定会社等の荷さばき施設等の整備に係る固定資産税等の軽減措置(10年間1/2)の2年間延長
(5)新関西国際空港(株)及び関空土地保有会社に係る特例措置の整備
・旧関空会社に措置されている用地造成費用に係る準備金制度の適用を関空土地保有会社へ変更した上、毎年度の損金算入限度額を見直し(所得の2/3等→所得の実質4/5等)
・新関空会社に係る環境対策用地取得のための登録免許税の非課税措置の創設
・新関空会社及び関空土地保有会社に係る固定資産税等(1/2)、法人事業税の軽減措置(資本割5/6)及び不動産取得税の非課税措置
・新関空会社に係る組織再編成による資産・負債の承継に係る法人税の所要の措置
(6)成田国際空港(株)の事業用資産に係る固定資産税等の軽減措置の2年間延長(4/5)
2.地域の経済活性化等
(1)長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(土地、貨物鉄道車両等)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について圧縮記帳による課税の繰延べ(80%)を認める買換特例について、買換資産に一定の要件を付したうえで3年間延長(法人税、所得税)
(2)中小企業が行うトラック、内航貨物船その他機械装置等の設備投資を促進するため、法人税等に係る中小企業投資促進税制(特別償却30%又は税額控除7%)の2年間延長
(3)観光立国推進のため、ホテル・旅館の建物について、使用実態等を踏まえ、平成27年度の評価替えにおいて固定資産評価を見直し(固定資産税)
◎低炭素・循環型社会関連税制
1.省エネ・グリーン化の推進
(1)認定省エネ住宅(仮称)の普及促進のため、以下の措置を創設。
・住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ(平成24年度3,000万円→4,000万円、平成25年度2,000万円→3,000万円。最大控除額まで所得税額が控除されない場合は翌年度の個人住民税額から控除)
・所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)、所有権移転登記(一般住宅0.3%→0.1%)に係る軽減税率(登録免許税)
(2)モーダルシフト促進のため、JR貨物が鉄道貨物輸送の効率化のための取得した機関車・コンテナ貨車に係る軽減措置(5年間3/5)の2年間延長及びJR貨物が第三セクターから借り受ける輸送力増強のための鉄道施設に係る固定資産税の軽減措置(10年間1/2)について現在実施中の事業への適用
2.自動車の車体課税の見直し
(1)環境性能の優れた自動車(エコカー)について自動車重量税のいわゆる「当分の間税率」を廃止し、その他の経年車(13年未満)について当分の間税率を900円/0.5t・年軽減
(2)エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、以下の見直し・拡充を行った上で3年間延長
・新たな燃費基準に基づき区分を再編し、ハイブリッド車の燃費性能に匹敵するガソリン自動車を新たに免税の対象に追加
・自動車重量税について本則税率を適用した上で、自動車重量税・自動車取得税を次のとおり減免
2015年度燃費基準+20%達成車=初回:免税、2回目:50%軽減
2015年度燃費基準+10%達成車=初回:75%軽減
2015年度燃費基準達成車=初回:50%軽減
(3)グリーン化特例(自動車税)について、新たな燃費基準に基づき区分を再編した上で2年間延長(2015年度燃費基準+10%達成車=50%軽減、基準達成車=25%軽減)
(4)先進安全自動車(ASV)のうち、衝突被害軽減ブレーキを備えた大型トラックに係る特例措置(自動車重量税:50%軽減、自動車取得税:取得価額から350万円控除)の創設
(5)ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシーに係る特例措置(自動車重量税:免税、自動車取得税:取得価額から車種毎に一定額控除)の創設
◎子育て・医療・介護等税制
・子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置(所得税、個人住民税等)
・子ども・子育て新システムの構築に伴い、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合には、新たに位置づけられる給付について非課税措置及び差押禁止措置を講じる。
・社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 (事業税)
・医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続 (事業税)
・社会保険診療報酬の所得計算の特例(いわゆる「4段階税制」) (所得税)
・研究開発税制(増加型・高水準型)の延長 (所得税、法人税、法人住民税)
・国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ(たばこ税、地方たばこ税)
◎年金税制
・事業主が存在しない等の理由によって企業年金等に移行できない適格退職年金に関する税制優遇措置の継続
(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税)
平成23 年度末で廃止期限を迎える適格退職年金のうち、事業主が存在しないもの、厚生年金保険未適用事業所の事業主が締結しているものについては企業年金等に移行できないことから、廃止期限を過ぎた平成24 年度以降も、現在の税制優遇措置を継続適用します。
◎金融関連の東日本大震災復興支援に関する措置
・地方公共団体が委託者となる土地信託に係る登録免許税等の非課税措置
信託会社等が東日本大震災により著しい被害を受けた一定の地方公共団体との信託契約に基づき、その地方公共団体の所有する土地の上に一定の施設を建築する場合において、その施設の用に供する土地及び建物の所有権に係る信託の登記に対する登録免許税を非課税とする。
・日本版レベニュー債の非課税債券化等
・「非居住者債券所得非課税制度」について、非課税の対象外とされる「利益連動債」の範囲から、東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に「完全支配関係」がある公社等が発行する「利益連動債」(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)を除外する。
(注)
「非居住者債券所得非課税制度」:海外投資家が受ける振替公社債の利子を非課税とする制度。
「日本版レベニュー債」:地方公共団体との間に完全支配関係(発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係)がある公社等が発行する債券で、その利子が当該公社等の利益等に連動するもの(利益連動債)をいう。有料道路、公営住宅等のインフラを整備する資金を調達する目的で発行されることが想定される。
◎金融資本市場の基盤整備に関する措置
・金融商品に係る損益通算範囲の拡大
平成26年に上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率が20%本則税率となることを踏まえ、その前提の下、平成25年度税制改正において、公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算範囲の拡大を検討する。
・少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(日本版ISA)の利便性向上・事務手続の簡素化に向けた所要の措置
非課税口座年間取引報告書に記載すべき事項のうち繰越取得対価の額の記載を不要とする。また、非課税口座開設確認書の交付申請書と非課税口座開設届出書について、これらの書類を同時に金融商品取引業者等の営業所の長に提出できる取扱いとする。
・国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)
国際課税原則については、OECDモデル租税条約の改定等を踏まえ、様々な産業における実態等を考慮しつつ、「総合主義」に基づく従来の国内法上の規定を「帰属主義」に沿った規定に見直すとともにこれに応じた適正な課税を確保するために必要な法整備に向け、具体的な検討を行う。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[財務省]
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf