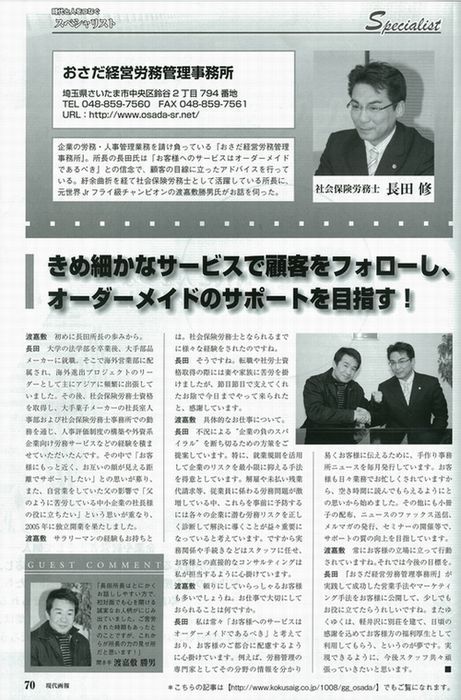本年2月から厚労省では、パートタイム労働をめぐる実態と課題を整理するとともに、今後のパートタイム労働対策について見当を重ね、この程、その報告書がまとめられました。これは、平成20年4月に「改正パートタイム労働法」の施行に際し、3年経過後に施行状況を踏まえ見直しを行うとされていたことによるものです。
■報告書の概要
報告書では、パートタイム労働者と通常の労働者との均衡待遇の確保を一層促進していくとともに、均等待遇を目指し、パートタイム労働者の能力を有効に発揮できる社会の実現に向けた今後の対策の在り方についての議論をまとめています。
具体的には、パートタイム労働者の雇用管理の改善をより一層進めるため、通常の労働者との間の待遇の異同、待遇に関する納得性の向上、教育訓練の実施、通常の労働者への転換の推進などについての課題を分析し、考えられる論点を整理したものとなっています。
◎検討に際しての基本的考え方
(1)パートタイム労働者の公正な待遇の確保
パートタイム労働者は増加する一方、通常の労働者との間に待遇の格差が生じているが、両者の間で、職務、働き方や待遇の決定方法が異なることが一つの理由と考えられる。このような日本の雇用システムの特徴を踏まえながらも、パートタイム労働者についても働き・貢献に見合った公正な待遇を実現するため、平成20年4月から改正パートタイム労働法が施行されている。しかしながら、通常の労働者とパートタイム労働者の間に依然として待遇の格差が存在する中で、パートタイム労働者も含めて労働者の働き・貢献に見合った公正な待遇をより一層確保していくことは、社会の公正という観点から、極めて重要である。
(2)パートタイム労働者が能力を発揮する社会
人口減少社会を迎えようとしており、今後、ますます労働力供給が制約される日本では、「全員参加型社会」の実現に向け、若者、女性、高齢者、障害者をはじめ就労を希望する者の支援を進めることが重要な課題となっている。一方、短時間労働は、様々な事情により就業時間に制約のある者が従事しやすい働き方として、また、ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方として、位置付けることができる。したがって、パートタイム労働者が能力を十分に発揮できるような条件を整備しつつ、その積極的な活用をしていくことは、女性や高齢者の就業拡大にもつながることが期待される。その条件整備として、パートタイム労働者の均衡待遇の確保を一層促進していくとともに、均等待遇を目指していくことが必要である。
(3)パートタイム労働者の多様な就業実態や企業の雇用管理制度等を踏まえた対応
今後のパートタイム労働対策の在り方については、パートタイム労働者や通常の労働者の多様な就業実態や、企業の雇用管理の多様な実態を踏まえ、きめ細かく対応できる方策を検討する必要がある。
◎パートタイム労働の課題
(1)通常の労働者との間の待遇の異同
ア.差別的取扱いの禁止(第8条)
3要件に該当するパートタイム労働者は、実態調査によると、調査対象パートタイム労働者の0.1%となっているが、今後、第8条の規定を活用してパートタイム労働者の雇用管理の改善を進める余地は小さい状況となっている。日本の雇用慣行の下、3要件がパートタイム労働者の均等待遇の確保を図る手段として合理性を有しているか、単に企業のネガティブ・チェックリストとして機能しているのではないか、また、あらゆる待遇につき一律に3要件が不可欠となるのかなどの点を含め、その在り方について検討する必要があると考えられる。
イ.均衡待遇の確保(第9条)
賃金に対する不満・不安を持つパートタイム労働者も多く、パートタイム労働者の待遇改善に対するニーズは高いと考えられ、同時に、都道府県労働局雇用均等室による是正指導も一定程度実施していることから、より一層の待遇改善を推進する方策について検討する必要があると考えられる。
(2)待遇に関する納得性の向上(第13条)
パートタイム労働者が、事業主に対し説明を求める潜在的なニーズは一定程度あると考えられるが、実際には、事業主に説明を求めることが必ずしも容易でない状況がうかがえる。このため、「パートタイム労働者からの求め」という要件が必要であるかどうかも含めて、パートタイム労働者の納得性をより一層向上させる方策を検討する必要があると考えられる。
(3)教育訓練(第10条)
パートタイム労働者が従事する職務に必要な導入訓練は、事業所で一定程度実施されている一方、キャリア形成のための教育訓練については、必ずしも十分に行われていない。このため、教育訓練を通じてパートタイム労働者のキャリア形成を促進していくための方策を検討する必要があると考えられる。
(4)通常の労働者への転換の推進(第12条)
通常の労働者への転換推進措置を実施している事業所は約半数となっていること等から、その更なる推進が必要であると考えられるとともに、雇用の安定を志向する一方で、様々な事情により、勤務時間や日数が柔軟な働き方を自ら選択しているパートタイム労働者のニーズに応える方策があるかどうかについて検討する必要があると考えられる。
(5)パートタイム労働法の実効性の確保(第16条、第21条、第22条)
パートタイム労働法の実効性をより一層確保するため、紛争解決援助の在り方等について検討する必要がある。
(6)その他(税制、社会保険制度等関連制度)
就業調整を行っているパートタイム労働者は4人に1人いるが、就業調整は、パートタイム労働者の職業能力の発揮や待遇の改善を阻害していると考えられる。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]