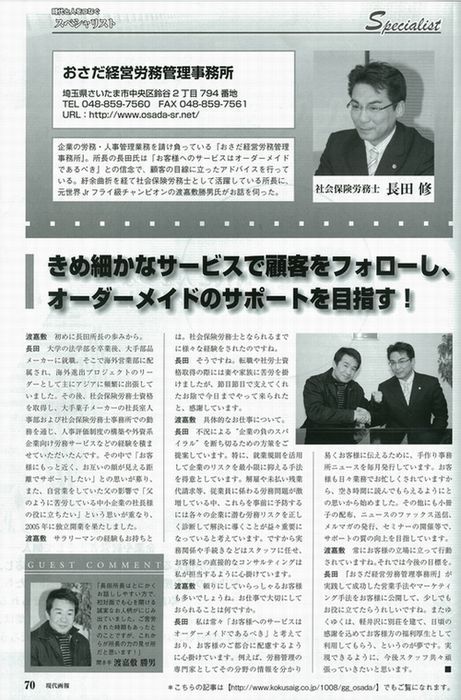年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。この程、国税庁から平成23年分年末調整の仕方について公表されました。
■昨年から変わった点とは?
1.扶養控除の見直しが行われました
(1)年齢16歳未満の扶養親族(以下、「年少扶養親族」という)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」という)とすることとされました。
(2)年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
(3)源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。
(注)「扶養親族」とは、居住者と生計を一にする次の人(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
(ア)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
(イ)児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子
(ウ)老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人
2.同居特別障害者加算の特例措置が改組されました
(1)年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました。
(2)給料や賞与に対する源泉徴収税額は、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含みます)又は同居特別障害者に該当するときは、従前どおり、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
(注)「同居特別障害者」とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
| 区 分 | 控除額 | ||
| 配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 380,000円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 480,000円 | ||
| 扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族(※) | 380,000円 | |
| 特定扶養親族(※) | 630,000円 | ||
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 480,000円 | |
| 同居老親等 | 580,000円 | ||
| 障害者控除(注2) | 一般の障害者 | 270,000円 | |
| 特別障害者 | 400,000円 | ||
| 同居特別障害者(※) | 750,000円 | ||
(注)1 上記表中(※)印を付した箇所が改正された項目です。
2 障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。
3.給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、所要の経過措置を講じた上で、平成22 年12 月31 日をもって廃止
(1)給与所得者等が自己の居住の用に供する住宅等の取得に関して、その使用者等から受ける次の経済的利益等で、平成22年12月31日までの間に係るものについては、使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益等の水準を著しく超える部分を除き、所得税が課されないこととされています。
(ア)住宅等の取得に要する資金に充てるために、使用者から使用人である地位に基づいて無利息又は低い金利により資金を借り受けた場合の経済的利益
(イ)住宅等の取得資金を金融機関等から借り受けている場合の利子の支払に充てるために、その利子の全部又は一部に相当する金額を、使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合の利子補給金
(ウ)勤労者財産形成促進法に基づき、使用者や事業主団体が講ずる負担軽減措置等により受ける経済的利益や補給金
(2)改正により、本特例については平成22年12月31日をもって廃止されました。
なお、同日以前に使用者等から住宅資金の貸付け等を受けている人に対しては、引き続き本特例を適用するための所要の経過措置が講じられました。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm